保育の心理学4 アイゼンバーグ、コールバーグ、(ピアジェの認知発達段階もいっしょに)保育の心理学の人名を覚えよう
保育の心理学2 ローレンツ、ポルトマン、バルデス、ゲゼル、シュテルン語呂合わせ
フロイトってどんな人?フロイトの3つの理論を簡単に覚える
フロイトは心理学を学んでいない人でも一度は耳にしたことがある人物ではないでしょうか。およそ100年以上前に、医師で人間の精神分析について学問にしたパイオニア的存在です。
主なキーワードは、無意識、リビドー、心理性的発達段階、エス・自我・超自我などです。
心の構造理論(イド・自我・超自我)とは?
フロイトは、人の心を3つの構造に分けて説明しました。
| 構造 | 読み方 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| イド(Id) | いど | 本能・欲求 | 「快」を求める。赤ちゃんのように本能で動く |
| 自我(Ego) | じが | 現実との調整役 | イドの欲求と現実や社会のルールをすり合わせる |
| 超自我(Super Ego) | ちょうじが | 良心・道徳 | 善悪を判断し、行動をコントロールする |
覚えるイメージと語呂合わせ
- イド=赤ちゃん:泣いたらすぐ欲しい
- 自我=保育士:現実と子どもの要求を調整する役
- 超自我=保護者や社会のルール:してはいけないことを教える存在
「イジするのチョーむり」
イメージは、保育園児を育てる母の心の声!!!こんな感じです
イド(本能):「おいしそう!食べたい!今すぐ!」
自我(現実調整):「今は授業中だから、おやつはあとでね」
超自我(道徳):「人の物を勝手に食べちゃダメだよ」ってムリー!!!
心理性的発達理論(5段階)を順番で暗記

フロイトは発達段階を段階ごとに分けました、これがまた独特なネーミングで、、、
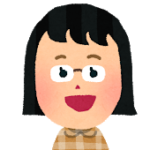
口唇期 → 肛門期 → 男根期 → 潜伏期 → 性器期
→ この順番はそのまま問題になることが多いため、語呂合わせで丸暗記が効果的!
「こもだくん、もぐってせいこう!!」
- 口唇期 こ
- 肛門期 も
- 男根期 だ(くん)
- 潜伏期 もぐって
- 性器期 せい(こう)
無意識の役割とその重要性(フロイト理論)
フロイトによれば、人間の心は「氷山のような構造」をしており、大部分(90%以上)は“無意識”の領域にあると考えられています。
意識(海面上) ← 氷山の先端
前意識(海面すぐ下)
無意識(深海)← フロイトが最重視
無意識が重要な理由
- フロイトは「人間は理性だけで動いていない」ことを明らかにした人物
- 他の理論(ピアジェやエリクソン)は「意識的な成長」を重視しており、フロイトだけが「無意識」の重要性を説いたことがポイントになります。
保育の心理学試験に頻出
平成30年(2018年)前期「保育の心理学」より
問題:
次の記述は、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)に関するものである。適切なものを1つ選びなさい。
- 発達段階を「感覚運動期」「前操作期」などに分けた。
- 発達を「口唇期」「肛門期」「男根期」などに分けた。
- 「最近接発達領域」の概念を提唱した。
- 道徳性の発達段階に注目し、「前慣習的段階」「慣習的段階」などに分類した。
- 発達を「基本的信頼感 vs 不信感」などのライフステージごとに示した。
正解:2
→フロイトは性格発達段階を「口唇期→肛門期→男根期→潜伏期→性器期」に分けました。
令和4年(2022年)前期「保育の心理学」より
問題:
次のうち、フロイトの心理性的発達理論に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 肛門期は自己主張が強くなる時期である。
- 口唇期は思春期に該当する。
- 男根期は性的関心が沈静化する時期である。
- 潜伏期は排泄のしつけと関連が深い。
- 性器期はアイデンティティの確立と関連がある。
正解:1
→肛門期(1歳半~3歳頃)は、排泄を通じて「自律性」を学ぶ時期。自己主張や我の芽生えが見られます。
まとめ
フロイトの精神分析は奥が深くていつも新鮮さを覚えます。根本的に人間は何も変わらないのですね。ほかにも保育の心理学で頻出の外国人の語呂合わせをまとめているのでぜひ参考にしてください。
保育の心理学3 エリクソンの発達理論、フロイト、ハヴィガースト、バルデス、マズロー
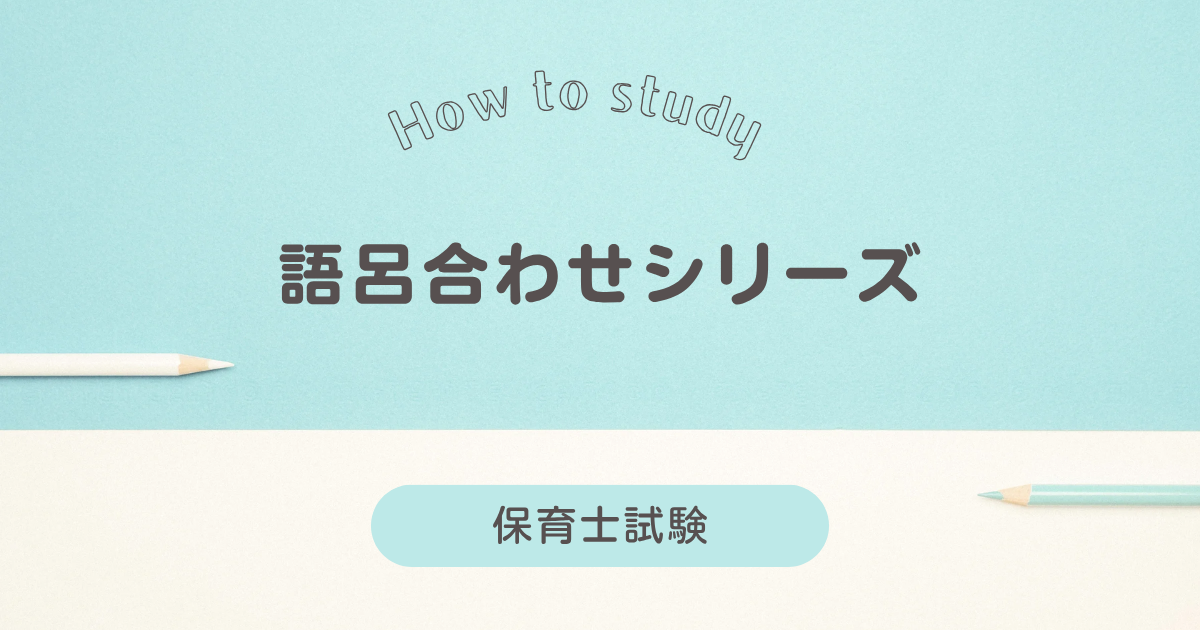
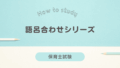
コメント